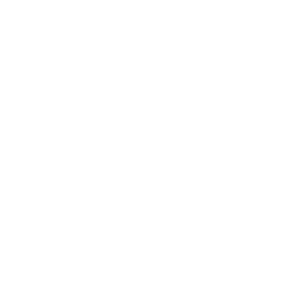こども誰でも通園制度とは?概要や試行的事業の内容を解説
中でも、2024年度から段階的に始まり、2026年より本格的にスタートする、こども家庭庁が進める「こども誰でも通園制度」は、子育て家庭の負担軽減と子どもの成長に大きく貢献する制度として注目を集めています。
この記事では「こども誰でも通園制度」とはどのような制度なのか、詳しく解説していきます。
こども誰でも通園制度とは?

こども誰でも通園制度は、保護者の就労状況にかかわらず、0~2歳児が保育施設を利用できる新しい制度です。2026年度からの本格実施を目指し、現在試行事業が行われている少子化対策の一環として、子育て家庭の多様なニーズに応え、子どもの成長と子育て負担の軽減を目的としています。
従来の保育制度では、保護者の就労が保育施設利用の必須条件でした。しかし、こども誰でも通園制度は、就労の有無を問わず、全ての子育て家庭が利用できる点が大きな特徴です。これにより、これまで保育サービスの対象外であった、専業主婦(夫)家庭や求職中の家庭なども、保育施設を利用できるようになります。
制度を設ける目的
近年、核家族化や地域コミュニティの希薄化により、子育て家庭の孤立が社会問題となりつつあります。特に、0~2歳児を持つ家庭では、子どもが保育所などに通っていない場合、保護者が社会とのつながりを築きにくく、育児負担や精神的ストレスを抱えやすい傾向があります。こども誰でも通園制度は、こうした子育て家庭の孤立を防ぎ、子どもに多様な刺激と成長の機会を提供することで、より良い子育て環境の実現を目指しています。
具体的には、以下の目的が掲げられています。
1.子育て家庭の孤立感・不安感の軽減
保育施設での交流を通じて、保護者が他の保護者や保育士とつながり、子育てに関する情報交換や相談ができる場を提供することで、孤立感や不安の解消の場とすることが目的とされています。
2.子どもの発達支援
家庭以外の環境で、同年代の子どもたちと触れ合う機会を設けることで、社会性や協調性、コミュニケーション能力など、子どもの発達を多角的に支援します。
3.多様な保育ニーズへの対応
従来の保育制度では、就労している保護者のみが利用対象でしたが、本制度は就労の有無にかかわらず利用できるため、多様な家庭環境やライフスタイルに対応した保育サービスを提供できます。
現在、全国の自治体で試行事業が行われており、制度の具体的な運用方法や効果の検証が進められています。試行事業の内容は自治体によって異なります。利用対象年齢、利用時間、利用料、提供されるサービスなどがさまざまのようです。
試行事業を通じて、制度の課題や改善点も明らかになってきています。例えば、保育士の確保や施設の整備、多様なニーズへの対応など、本格実施に向けて解決すべき課題が山積しているようです。試行的事業から読み解くこども誰でも通園制度の具体的な内容

試行事業の内容は自治体によってさまざまですが、以下の内容が軸になっています。
・対象年齢:0歳6ヶ月~2歳児
・利用時間:月10時間程度を想定
(ただし、試行事業や各自治体によって異なる場合があります)
・利用料:試行事業では1時間あたり300~400円程度が目安
(こちらも各自治体によって異なります)
・実施主体:市町村
「一般型」と「余裕活用型」の違い
こども誰でも通園制度には、「一般型」と「余裕活用型」の2つの運営形態があります。
一般型
保育所などの定員とは関わりなく、定員設定を自由に行う方法で制度独自の定員枠を設けています。また、こども誰でも通園制度専用の保育を実施します。
人員配置基準は、0歳児3人につき保育従事者1人以上、1~2歳児6人につき保育従事者1人以上です。既存の保育定員に影響されない点がメリットですが、新たな職員確保が必要となる点がデメリットです。
特徴としては、実質的にこども誰でも通園制度の職員と保育所などの職員が合同で対応することができることがあげられます。また、専門の部屋がある場合は、専任の職員のもとでの対応も可能です。
余裕活用型
既存の保育定員の空き枠を活用して、こども誰でも通園制度の保育を実施します。人員配置は通常の保育士配置基準に準じ、新たな職員確保が不要な点がメリットですが、定員に空きがない場合は実施できない点がデメリットです。
特徴としては、子どもが在園児と関わる機会が多く、定員の範囲内で受け入れるため、一般型と比べると職員を比較的確保しやすいことがあげられます。
実施している自治体の確認方法について
自治体がこども誰でも通園制度の試行事業を実施しているかどうか確認する際は、まずこども家庭庁のWebサイトを訪問しましょう。こども誰でも通園制度に関する基本的な情報や、試行事業の実施状況の概要が掲載されています。
ただし、具体的な内容や利用方法などは自治体ごとに異なるため、概要を掴んだら、次は各自治体のWebサイトを訪問してみるとよいでしょう。多くの自治体では、子育て支援や保育に関するページで、こども誰でも通園制度の試行事業について案内しています。
また、地域の保育関連団体や子育て支援センターなども情報源となります。保育関連団体や子育て支援センターは、地域の子育て支援に関する情報を幅広く提供しているため、こども誰でも通園制度の最新情報や制度の利用、導入の検討などの相談にも応じてくれる場合があります。試行的事業を実施している千葉市の例
千葉県千葉市では、こども誰でも通園制度の試行的事業を実施しています。
利用対象は市内または市外に在住の0歳6ヶ月~就学前の乳幼児で、月10時間を上限とし、1時間単位で利用可能です。利用料は、1時間あたり300円で利用できます。
利用にあたっては事前の登録が必要で、空き状況によっては希望日に利用できない場合もあります。時間が余ったとしても翌月には繰り越しはできません。
また、利用にあたっての注意点もいくつかあります。
・市外に住民登録がある場合、申請できません。
・同じ月に複数の実施施設を利用することはできません。
・事前登録をしても、申し込み状況により利用できない場合があります。
・施設の受入体制などの事情により、ご希望に添えない場合もあります。
・送り迎えは、保護者の方が責任を持って行います。
こども誰でも通園制度の本格実施までの道のり

2026年度の本格実施に向け、こども誰でも通園制度の具体的な内容や運用方法については、現在も検討が続けられています。一方で、関係法令の整備や予算措置、自治体への支援体制の構築など、解決すべき課題が多く残されています。
こども誰でも通園制度がスムーズにスタートするためには、まずは子ども・子育て支援法に基づいて、各地域で子ども・子育て支援事業として制度化することが急務といえます。
制度化にあたっては実施自治体の増加をはかり、本格実施に向けて検討が必要な各論点については、専門家を集めた検討会が実施されています。
また、試行的に実施することで事例を集め、その事例をもとに、本格始動する際の利用時間、利用可能枠の在り方、人員配置、設備運営基準、安定的な運営の確保など、こども誰でも通園制度を実施する上での必要事項の手引きになるようなものを作成していく必要もあります。
こども誰でも通園制度と一時預かり事業の違い
こども誰でも通園制度と一時預かり事業は、どちらも保護者が子どもを一時的に保育施設に預けることができる制度ですが、その目的、対象となる児童、利用時間、費用、利用方法などに違いがあります。それぞれの制度の特徴を理解し、適切に使い分けるのが良いでしょう。
・こども誰でも通園制度
子育て家庭の孤立防止、子どもの発達支援、多様な保育ニーズへの対応を主目的としています。子どもに集団生活の場を提供することで、社会性や協調性、コミュニケーション能力などを育み、心身の発達を促進することを目指しています。保護者にとっては、育児負担の軽減や、他の保護者や保育士との交流を通して、子育てに関する情報交換や相談の機会を得る場としての役割も期待されています。
・一時預かり事業
保護者の就労の有無にかかわらず、保護者の疾病、出産、冠婚葬祭、育児疲れの解消、リフレッシュなど、さまざまな理由で一時的に家庭での保育が困難になった場合に、子どもを預かるサービスです。あくまでも一時的な保育ニーズに対応するための制度であり、子どもの発達支援や子育て家庭の孤立防止といった目的は含まれていません。
一時預かり事業では、保育所や認定こども園などに通っていない乳幼児だけでなく、既に在園している子どもも利用できます。年齢の上限は施設によって異なりますが、小学校就学前までを対象としている場合が多いです。
さらに、利用時間は施設によって異なりますが、1日単位または時間単位で利用できます。利用時間の上限は特に設けられていない場合が多いですが、施設の空き状況や利用状況によって制限される場合があります。
料金は一般的には、1時間あたり500~1,000円程度の費用がかかります。自治体によっては、所得に応じて費用が減免される場合があります。
一時預かり事業を利用するには、事前に施設に問い合わせて空き状況を確認し、予約をする必要があります。利用方法は施設によって異なりますが、電話やWebサイトで予約を受け付けている場合が多いです。
以下、それぞれの制度の概要をまとめました
【こども誰でも通園制度】
目的:子育て家庭の孤立防止、子どもの発達支援、多様な保育ニーズへの対応
対象年齢:0歳6ヶ月~2歳児
利用時間:月10時間程度を想定(ただし、試行事業や各自治体によって異なる)
費用:1時間あたり300~400円程度
利用方法:システムでの予約を検討中
実施主体:市町村
【一時預かり事業】
目的:保護者の就労の有無にかかわらず、一時的に家庭での保育が困難になった場合に、子どもを預かるため
対象年齢:小学校就学前まで
利用時間:1日単位または時間単位(上限は特に設けられていない場合が多い)
費用:1時間あたり500~1,000円程度
利用方法:電話やWebサイトで予約
実施主体:市町村
どちらの制度も、一時的に子どもを預かる点には変わりはありません。ただし、実施している事業目的には大きな違いがあるといえます。
今後の展望

こども誰でも通園制度は、子育て支援の充実と少子化対策への貢献が大きく期待されています。試行事業を通して見えてきた課題を解決し、本格実施へとつなげることで、より多くの家庭が恩恵を受けられるよう、関係機関の尽力が求められています。
本格実施後は、さらなる質の向上と利用者の拡大を目指し、制度の改善や拡充が継続的に行われる見込みです。例えば、利用時間枠の拡大や、利用料の減免制度の拡充、対象年齢の拡大などが検討課題としてあげられます。
また、保育の質の向上という観点では、保育士の専門性向上のための研修制度の充実や、多様な保育ニーズに対応できる人材育成が重要となります。保育士の確保は急務であり、ICTを活用した保育記録システムの導入や、オンラインでの子育て相談の実施など、テクノロジーを活用した効率的な運営も期待されます。
さらに、地域の子育て支援ネットワークとの連携強化も重要な要素です。子育て支援センターや地域の子育てサークル、ファミリーサポートセンターなどとの連携を深めることで、多様な子育てニーズに対応できる体制を構築し、地域全体で子育て家庭を支える環境づくりを進める必要があります。
こども誰でも通園制度は、単に子どもを預かるだけでなく、保護者同士の交流促進や子育てに関する情報提供、相談支援など、子育て支援の軸のひとつの機能としても期待されています。
制度の普及と質の向上を通して、子育てしやすい社会の実現、ひいては少子化対策への貢献と同時に、保育現場の負担軽減や保育士の処遇改善といった課題にも取り組む必要があるでしょう。
また、制度自体の認知度をあげるための周知活動も今後の課題です。より多くの方が利用できるように広めていくことも必要になるでしょう。
まとめ
こども誰でも通園制度は、子どもを育てる家庭にとって手助けになる制度のひとつではないでしょうか。
保育園関係者からすると、これから作り上げていく制度でもあるので、不安もあるかと思います。制度への理解を深め、円滑に運営できるよう、2026年の本格的なスタートに向けて準備をしていきましょう。

保育に関わる方たちとの交流を通じて、役に立つ情報を発信していきます。
関連記事一覧

最新記事