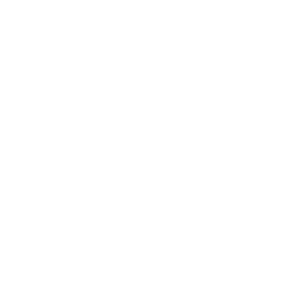保育士の有効求人倍率はどのくらい?保育士不足の実態を知ろう
保育園を志望する子どもの数に対して、保育園が不足している現状を打開しようと保育園を新設する動きがある一方で、そこで働く保育士が不足している状況です。
保育士不足や待機児童問題、保育士不足を問題視した政府は、保育士の処遇改善などを積極的に行っています。
実際に、保育士がどの程度不足しているかを考える際に役立つのが「有効求人倍率」です。
今回は、保育士の有効求人倍率について、詳しく解説します。
保育士の有効求人倍率は実際どのくらい?

まずは「有効求人倍率」という言葉の意味を確認しておきましょう。
有効求人倍率とは
有効求人倍率とは、求職者1人あたり、何件の求人があるかを示す数値です。
保育士の有効求人倍率の場合、仕事を探している保育士志望者に対して、勤務先となる保育園が求めている保育士数の割合がどのくらいかを知る指標となります。
例えば、有効求人倍率が4倍の場合は、1人の求職者に対して4件の求人があるということになります。
このように、有効求人倍率が高い状況は、求職者側からすると就職しやすい状況、採用する側からいうと応募者が少ない状況で、人手が不足している状況といえるのです。
【算出方法】
有効求人倍率は
有効求人倍率=求人数÷求職者数
という計算式で求めることが可能です。
100件の求人件数に対して、100人の応募があったとしたら、
100÷100=1
ですから、有効求人倍率は1倍です。
つまり、求人数と応募者数のバランスがちょうど良いという計算になります。
【有効求人倍率が低い状況】
では、有効求人倍率が低いというのはどのような状態でしょうか。
例えば、100件の求人情報に対して、200人の応募があった場合は
100÷200=0.5
となり、有効求人倍率は0.5倍です。
→求人数に対して応募者数が多く、2人に1人しか採用されない状況となります。
有効求人倍率が低い状態であり、求人数が不足している、つまり保育士の数は充足している状況といえるのです。
【有効求人倍率が高い状況とは】
100件の求人情報に対して、50人の応募があった場合は
100÷50=2
となり、有効求人倍率は2倍です。
→求人数に対して、応募者数が少ないということになります。
100件の求人に対して50人しか応募がなく、有効求人倍率が高い状況ですから、人手不足の状況に陥っていると判断できます。
2024年1月の保育士の有効求人倍率
厚生労働省の発表によると、2024年1月時点で保育士の有効求人倍率は3.54倍でした。
全職種平均は1.35倍となっていますから、保育士の有効求人倍率は高い水準で推移していることが分かります。
データで見る!保育士の有効求人倍率
厚生労働省が発表している保育士の有効求人倍率を見ていきましょう。
都道府県別
まずは、2024年1月時点の都道府県別有効求人倍率です。
都道府県 | 有効求人倍率 |
北海道 | 2.28倍 |
青森 | 1.67倍 |
岩手 | 1.71倍 |
宮城 | 3.61倍 |
秋田 | 1.82倍 |
山形 | 2.01倍 |
福島 | 3.2倍 |
茨城 | 4.73倍 |
栃木 | 7.9倍 |
群馬 | 2.14倍 |
埼玉 | 4.03倍 |
千葉 | 2.7倍 |
東京 | 4.06倍 |
神奈川 | 2.99倍 |
新潟 | 2.66倍 |
富山 | 3.06倍 |
石川 | 3.29倍 |
福井 | 4.13倍 |
山梨 | 3.09倍 |
長野 | 2.8倍 |
岐阜 | 3.98倍 |
静岡 | 5.27倍 |
愛知 | 4.38倍 |
三重 | 2.84倍 |
滋賀 | 4.94倍 |
京都 | 2.96倍 |
大阪 | 4.27倍 |
兵庫 | 3.33倍 |
奈良 | 4.85倍 |
和歌山 | 4.14倍 |
鳥取 | 2.8倍 |
島根 | 2.16倍 |
岡山 | 5.38倍 |
広島 | 6.55倍 |
山口 | 1.92倍 |
徳島 | 4.86倍 |
香川 | 4.19倍 |
愛媛 | 4.31倍 |
高知 | 1.63倍 |
福岡 | 3.55倍 |
佐賀 | 2.93倍 |
長崎 | 2.73倍 |
熊本 | 2.69倍 |
大分 | 2.37倍 |
宮崎 | 2.43倍 |
鹿児島 | 3.15倍 |
沖縄 | 3.9倍 |
全国で見ると、有効求人倍率の1位は栃木県で7.9倍。1人の保育士に対して、約7.9件の求人があります。ついで2位が広島県6.55倍、3位が岡山県5.38倍。
保育士の人手不足は都市部に多いと考えられがちですが、意外とそうでもないようです。このように比較してみると、全国平均を上回っている地方が多いことを確認できます。
2021年以降の有効求人倍率
2021年~2024年における保育士の有効求人倍率は、全国平均では以下のようになっています。
2021年:2.94倍
2022年:2.93倍
2023年:3.16倍
2024年:3.54倍
保育士の有効求人倍率は依然として高い傾向にあり、保育士が不足している状況が継続していることが分かります。
2021年、2023年は、コロナ禍による生活スタイルの変化が関係し、減少傾向にありました。しかし、2023年から現在まで再び上昇傾向にあります。さらに2025年には待機児童のピークが来るとの予測、2026年度に実施が見込まれている「こども誰でも通園制度」の導入もあり、今後も保育士の需要が高まる可能性があります。
保育士の有効求人倍率が高い傾向にある背景
保育士の有効求人倍率は、他業種と比較しても高い数値を維持しています。また、近年さらに増加傾向にあります。
その理由としては以下の背景が挙げられます。
社会の変化による需要の増加
共働き世帯の増加や、祖父母世代との同居が難しい核家族の増加など、子育て環境の変化は大きな理由のひとつといえます。
夫婦がフルタイムで働き、サポートしてくれる祖父母などがいない場合、早朝や夕方以降まで長時間保育を行っている保育園の役割が大きく、保育士の需要も高まりました。
新規園や定員増による求人数増加
保育園の需要の高まりにより、待機児童問題が発生し、それらを解消するため、都市部を中心に新規園の開園や定員増加の試みが行われてきました。
その一方で、新卒保育士の人数はあまり増加しておらず、保育士の数が保育園の求人数に追いついていない現状があります。
より良い人材を確保するためには

採用する保育園としては「優秀な保育士に継続して勤務して欲しい」というのが本音だと思います。
しかし、実際には保育士の資格を取得しても、約30パーセントの人が保育の仕事には就かない状況が続いています。
保育士の資格を持ちながらも、保育の仕事をしていない人を「潜在保育士」と表現します。
潜在保育士になるケースには、具体的に以下のようなものがあります。
・資格を取得して学校を卒業したものの、保育士にならない
・結婚や出産などのタイミングで離職し、その後保育士には復職しない
ではなぜ、潜在保育士は保育士として働く道を選ばなかったのでしょうか。
保育士業界の現状を知る
保育士業界は、人手不足やハードワークであること、低賃金であることなどが問題視されています。
テレビや新聞の報道などでも多く取り上げられていますから、それを目にして不安を感じ、潜在保育士となったケースもあるでしょう。
具体的には、以下のような点が特に問題として注目されています。
保育士志望者不足
テレビのニュースや報道などでも取り上げられている通り「保育士になりたい」という志望者数自体が減少傾向にあることが、有効求人倍率が高い理由のひとつといえるでしょう。
理由としては、やはり激務であることや、低賃金であることなどが挙げられます。
保育士ニーズの高まり
保育士不足の一方で、子どもを保育園に入園させたいと考える保護者が増加していることも、保育士ニーズが高まる理由のひとつです。
以前は、子どもが小さなうちは専業主婦として、家事や育児を担う専業主婦が多い傾向にありました。
しかし、最近は仕事を持つ女性も増加しています。
そうなると、子どもの世話をしてくれる人を探す必要がありますが、最近は核家族化が進み、祖父母世代にも頼れないケースが多いため、保育園に入れなければ仕事ができない状況の家庭が増えているのです。
こうした保育園不足解消のために、自治体では新規保育園設立や、保育定員を増やすなどの対応を取っています。
しかし、保育園の数が増えても、そこで働く保育士の数が不足しているというのが現状です。
保育士の待遇への不満
近年では大学や短期大学、専門学校といった指定保育士養成施設を卒業し、保育士資格を所有していても、保育士として就職しない人が増加傾向にあります。
2018年においては、保育士資格保有が必須となる施設に就職した、指定保育士養成施設卒業者は66パーセントであり、残り34パーセントは保育士としては仕事をしていない状況です。
また、保育士として就職をしても、5年未満で退職してしまうケースも多く見られます。
なぜ、このような状況になってしまうのでしょうか。
主な理由としては、
・幼い子どもの命を預かる、責任の多い大変な仕事であるにも関わらず、給料が低い傾向にあること
・持ち帰りの仕事が多く、休みを取りにくい環境であること
など、保育士を取り巻く厳しい環境が原因として挙げられます。
激務であるにも関わらず、労働条件が悪く、保育士として働きたいというモチベーションが低下してしまう傾向にあるのです。
こうした理由で保育士の資格を保有していても、それを活かして仕事をしない「潜在保育士」となってしまう事例が増えています。
保育士不足解消に向けた行政の対策
保育士不足解消に向けて、政府では2013年からスタートした処遇改善加算を進め、賃金アップやキャリアアップ支援に乗り出しています。
2013年に始まった処遇改善等加算Ⅰでは、保育士の勤続年数やキャリアアップ支援を実施し、2017年開始の処遇改善等加算Ⅱは、キャリアアップにさらに力を入れた形で支援するものとなっています。
また、2022年2月には2022年9月までの期間限定で、保育士・幼稚園教諭等処遇改善臨時特例事業が行われました。勤続年数やキャリアに関係なく、認可保育園等で働く全職員の収入を3%アップ、月額にしておよそ9,000円の賃上げを行う措置を実施しました。
期間が終了した2022年10月からは、「処遇改善加算Ⅲ」として継続しており、制度の終了日は未定です。
このように、深刻な保育士不足に対して、政府もさまざまな取り組みを実施しているのです。
では、自治体ではどのような取り組みが行われているのでしょうか。
就職一時金および定着支援金支給
保育士として就職した際に支払われる就職一時金や、勤続年数によって定着支援金などの支給を実施している自治体もあります。
園が所在する自治体にそういった制度がある場合は、ぜひ活用してみてください。
手当支給
勤続年数に応じた手当支給なども、各自治体で積極的に行われています。
勤続年数が長ければ長いほど給与額が上がる仕組みですから、仕事へのモチベーションアップにつながる制度といえるでしょう。
こちらも、自治体が実施しているものとなります。こうした制度を実施している自治体に園がある場合は、ぜひ活用することをおすすめします。
家賃補助制度
家賃補助制度は、正式名称は「保育事業者宿舎借り上げ支援事業」といい、保育士のために社宅を借り上げている事業者(保育園)に対して実施されている支援制度です。
勤務している保育園がこの制度を利用して借り上げ社宅を保有している場合、保育士はその社宅に自己負担なし、またはそのエリアの平均家賃よりも大幅に安く住むことができます。
保育園側としても、求職者である保育士にアピールできるポイントとなるでしょう。
一例として東京都の場合を見てみると、補助基準額は一戸につき月額82,000円となっています。
ただし、家賃補助制度は、自治体によって実施の有無や割合が異なりますから、園のある自治体に確認が必要です。
このように、保育士の就・転職支援としては、政府として取り組んでいるものと、自治体が実施している支援が存在します。
園が所在する自治体は実施しているかを確認し、実施している場合は導入を検討して、保育士の福利厚生を充実させる一助にしてください。
保育士志望者が「この保育園に働きたい!」と感じる魅力のひとつになるはずです。
また、今後制度が変更されると利用できなくなる可能性もありますから、その点はあらかじめ把握しておく必要があるでしょう。
今後の保育士採用事情を考える
先述のように、政府は処遇改善を実施するなど、自治体も保育士確保のためにさまざまな支援に取り組んでいます。
その効果もあり、実際有効求人倍率は2015年の一番高い時期では東京で5.44倍だったものが、2022年では2.56倍と、少しずつ解消していることが分かります。
保育士にとって、現状は引く手あまたの状況であり、いかに「この園で仕事をしたい」と思ってもらえるかというのが保育園側の課題です。
2019年東京都保育士実態調査報告書によると、就業経験がある保育士の退職理由としては、以下の順位となっています。
1.職場における人間関係
2.給与が低い
3.仕事量が多すぎる
4.労働時間が長い
5.妊娠や出産など
最近は、男性保育士の数も増加傾向にありますが、それでも保育士という仕事は女性と関わることが多い職場となっています。
保育士同士はもちろんですが、保護者も母親が保育園との窓口となるケースが多く、そういった人たちとのコミュニケーションが良好に行えるかどうかは、保育士のモチベーションにも大きく影響するといえるでしょう。
風通しが良く、どんなことも相談しやすい職場環境を整えることが必要と考えてください。
給与面については政府や自治体の制度を活用することで、改善の助けとなるでしょう。
また、仕事量や労働時間に関してはICT化を進めることで事務作業を効率化し、短縮することが期待できます。
ICT化を推進することは、保育士同士の情報共有もスムーズにし、伝達ミス軽減にもつながります。
また、保護者とのコミュニケーションを円滑化することにも大変有効です。
妊娠や出産に関わる休暇については、結婚後も仕事を続ける女性が増えている社会情勢を考えても、休暇制度を整えることが必要と考えてください。
このように、できることから少しずつでも保育士にとって魅力的な園づくりをしていくことが、今後の保育士確保には欠かせません。
優秀な保育士に長く勤めてもらうためにも、保育士にとって居心地の良い職場環境づくりが重要であることを認識しておきましょう。
保育の多様化で保育士争奪戦はより厳しいものに
近年、共働き家庭の増加や少子化で保育は多様化し、保育園に限らず、さまざまな場所で保育士を求める施設が設置されるようになりました。
そのため、保育士が自分のライフプランに合わせた働きやすい職場を見つけたいと考え、就職先として保育園を選ぶ際の基準はより高いものに変わりつつあります。
質の高い保育士を確保するためには、労働環境が整った、働きやすい職場を用意することが急務です。
保育園としても、国や自治体の制度を最大限活用したり、ICT化を進めたりしながら、保育士により整った労働環境を整えていきましょう。

保育に関わる方たちとの交流を通じて、役に立つ情報を発信していきます。
関連記事一覧

最新記事