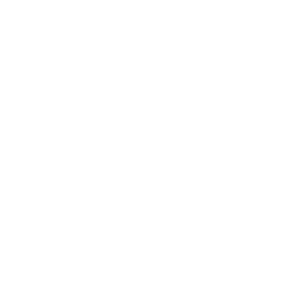【部分実習とは】指導案の書き方や保育学生が注意すべきポイント
「部分実習とはそもそも何をしたら良いのか?」「スムーズに段取り良くできるだろうか?」「子どもたちはついてきてくれるだろうか?」「担当の保育士にきちんと評価してもらえるだろうか?」「一部とはいえ責任重大でとても緊張してしまう!」など、多くの不安を抱えることでしょう。
こういた不安は、十分な計画と準備をすることで軽減することができます。
この記事では、部分実習における活動例と、実際の指導案の書き方や保育学生が注意すべきポイントをお伝えします。
準備をするうえでぜひ参考にしてください。
部分実習とは

保育士を目指して保育養成校に通う保育学生は、学校が定める期間に保育実習を行い、決められた単位を取得しなければいけません。
保育実習にはいくつか種類があり、段階を踏んで実習を行います。
■保育実習の中での位置づけ
部分実習は、保育学生が初めて実際に自分主体で保育を体験する重要な実習です。
保育実習には、以下の4種類の実習があります。
・観察実習
まずは現場観察をします。保育士や子どもたちの動きを観察して記録する実習で、1年生の最初の実習ではここから始まります。
・参加実習
実習先の担当保育士の指示に従って、保育に実際に関わります。
観察実習では見学要素が強いですが、参加実習では子どもたちとの関わりが多くなっていきます。
・部分実習
参加実習からさらに進み、保育の一部を任されます。
例えば、朝の会や午前の活動など、1日の流れの中での一部分を任されることになり、これらには十分な準備と指導案の提出が必要になります。
・責任実習
1日の保育の流れ全てを担当します。
実習先の担当保育士が見守りサポートしてくれますが、その日1日受け持ちのクラスを仕切ることになります。
実際には、学校の方針や実習受け入れ先の保育園によってもスケジュールが異なりますので、実習先の園で確認しましょう。
■部分実習の目的
部分実習を行う目的は、保育実習生が指示ではなく自分で考え、計画と準備をして指導する経験を積むことです。
保育実習生が保育士になった時に、実際に現場でどう動いていけば良いか、子どもたちとの関わり方や、プロとしてどのようなところに注意していかなければいけないかを、試行錯誤しながら学ぶのです。
実際にやってみないと、子どもたちの反応や適切な声掛けなどは体得できません。部分実習は、保育士になるための実践的な練習の第1歩といえるでしょう。
部分実習におけるおもな活動例

部分実習でどのような活動を行うか、経験が浅いうちは決めるのも一苦労なことだと思います。
クラスの年齢や特徴によっても変わってくるので、ある程度案が決まったら、詳細準備を進める前に担当の保育士に相談すると良いでしょう。
ここでは、一般的なおすすめの活動例をご紹介します。
・手遊び
朝の会や帰りの会、「いただきます」の前の少しの時間などに行うのは、手遊びがおすすめです。
保育の導入時や子どもたちを落ち着かせたい時など、保育のさまざまな場面で手遊びが行われています。
普段から、年齢・月齢別にさまざまな手遊びを用意しておくと良いでしょう。
このクラスで流行っている、子どもたちのお気に入り手遊びをチェックしておくのもおすすめです。
・絵本の読み聞かせ
絵本の読み聞かせは、活動時間が短めの場合でも実施できるためおすすめです。
1日の保育の中で、活動と活動の間に取り入れられることも多く、普段から子どもたちも慣れ親しんでいて、保育実習生が取り組みやすい部分実習のひとつです。
手遊び導入から絵本の読み聞かせといった組み合わせも良いでしょう。
絵本のチョイスは、年齢・月齢によってそれぞれふさわしい絵本も違ってきますので、それらを考慮し、よく吟味して選んでみましょう。
保育園にあるものを借りることもできますが、ご自身で持っているものを持ち込むことも可能です。
自分のものは読み慣れていて緊張が和らぐので、おすすめです。
読み聞かせの際は、はっきりと聞き取りやすい声で読めるように練習しておきましょう。
子どもたち全員の目線や位置など、見やすい配置などを考えて準備を整えてから始めます。
絵本の他、パペットやエプロンシアターなども良いかもしれません。
・制作遊び
午前中の設定保育を任せてもらえるなど、ある程度時間がある時におすすめなのが制作遊びです。
お絵描きやフィンガーペインティング、粘土、折り紙、廃材や身近な材料を使ったおもちゃや楽器制作など、いろいろ考えられます。季節にちなんだものの制作も良いですね。
年齢や発達によってできることが違ってきますので、担当保育士によく相談しましょう。
また、材料の調達にともない保護者からの協力が必要な場合がありますので、早めに計画を立てて動くことが大切です。
・運動やゲーム遊び
年齢が大きいクラスであれば、運動やゲームが可能になってきます。
身体を動かすことが得意な保育実習生にはおすすめです。
ただし、ケガやヒヤリハットを防ぐため、子どもの動きを予測し綿密な計画と準備が必要になります。
屋外活動であれば、悪天候の時の代替案も考えておきます。
年齢に応じた活動をチョイスするか、ルールを年齢によって難しくしたり優しくしたりなど調整します。
部分実習で必要となる「指導案」とは

部分実習では、「指導案」を作成し提出する必要があります。
「指導案」とは、実際に行う予定の保育活動の内容やねらい、子どもたちへの配慮や働きかけ、準備するものや環境設定などを詳細に記載します。
自分だけのメモではなく、他の保育士がそれを見て、どのようなねらいでどんな活動をするのか、どのような準備と当日の働きかけをすれば良いのか、などが分かるように記載しなければいけません。
部分実習の指導案を作る流れ
部分実習の指導案を作る流れは、実習先の保育園によって違うこともありますが、一般的な手順をお伝えします。
ステップ1:実習先の保育園の決まりや保育方針をチェックする
指導案を作成する前に、大前提として実習先の保育園の規則や決まり、保育方針はチェックしておきます。
規則や決まりを守ったうえでの活動が、子どもたちの安全を守ります。
また、保育方針にそった保育のねらいを作成すると良いでしょう。
ステップ2:担当のクラスの子どもたちの様子をチェックする
年齢や発達、クラスの人数などによって、活動内容や環境設定が異なりますので、クラスの人数の規模、子どもたちの関係などをチェックしておきます。
また、配慮が必要な子どもの情報も把握しておきましょう。
ステップ3:指導案を作成する
形式に従って、いよいよ指導案作成です。
保育園では、月案・週案・日案があらかじめ立てられているので、そこから大幅にずれないように注意します。
戸外活動であれば、悪天候時の案についても同時に作成します。
ステップ4:指導案を担当保育士に提出する
作成した指導案を担当保育士に提出し、アドバイスをもらいます。
保育士は多忙ですぐに見ることができるか分かりませんし、修正や微調整の時間も必要ですから、遅くとも部分実習の1週間前には提出しましょう。
ステップ5:フィードバックに応じて修正・再考する
いただいたアドバイスを元に、修正箇所があれば修正・再考します。
不安な時は、「アドバイスいただいたことを踏まえながら修正しているがこれで良いか?」を確認しながら進めていくと良いでしょう。
何度か修正する可能性を考え、早めの再提出を心掛けましょう。
ステップ6:最終提出及び代替え案を用意しておく
最終的な提出は、遅くとも部分実習の3日前には済ませておきましょう。
また、やむを得ない事情で万が一行えない場合の代替案も用意しておきます。
部分実習の指導案に書く内容

指導案を作成する流れが分かったところで、実際にどのような内容を書いていけば良いのか、見てみましょう。
指導案には、ねらい・活動内容・環境構成・子どもの動きと実習生の動きの4つを盛り込みます。
ひとつずつ解説します。
ねらい
設定した活動内容を通して、子どもたちに何を体験して何を学んでほしいのか、といった「ねらい」を明確にすることは非常に重要になります。
それが指導案の核の部分になるためです。
同じ活動でも「ねらい」が違えば環境構成や働きかけも違ってきます。
「ねらい」が定まることによって、おのずと環境構成や働きかけが決まってくるでしょう。
子どもの発達や興味、活動を通して何を得られそうかなどを考えて「ねらい」を決めましょう。
活動内容
実際に部分実習で行う遊びの内容を記載します。
ゲーム遊びであればゲームの内容やルール、制作遊びであれば何を作ってどう遊ぶのか、など詳細を記載しましょう。
環境構成
部分実習を行う際の、保育室の環境設定を具体的に記載します。
子どもの位置、椅子と机の位置、保育者や実習生の位置、用意する道具や備品の配置、音楽リズム遊びであればピアノの配置なども含めて、細かに明記しましょう。保育室の配置図を盛り込む場合もあります。
安全面で問題がないかどうか、子どもの動線や実習生が全体を見渡せるかなどを含め、安全に進められるかどうか、環境構成をしっかり考えて記載します。
子どもの動き・実習生の動き
予想される子どもの動きや言動と、実習生の働きかけや言葉掛けなどの対応について、事細かに記載しておきます。
しっかりと予想し、その対応を考えておくことは非常に重要です。
準備しておくことで自信がつき、慌てることなく行動できるなど、当日の部分実習がスムーズに行えます。
予想される子どもの姿や、それに対して実習生がどのようにサポートすれば良いのかを考えるには、普段から子どもたちの姿や保育士の動きをよく観察し、参考にしましょう。
部分実習を行う時に注意すべきこと

保育実習生が実際に部分実習を行うにあたり、どのようなことに注意すべきか、3つのポイントをお伝えします。
担当保育士に事前にしっかり相談しておく
担当保育士に部分実習の計画段階からこまめに相談しましょう。
日程があらかじめ決まっていれば、出来るだけ早く原案を提出して相談することで、いただいたアドバイスに対して修正する時間ができ、より良いものになるでしょう。
また、早い段階から部分実習を意識して実習に臨むことで、子どもたちの様子や友達関係、配慮するべきことや保育士の動きをしっかり観察して、部分実習に活かすことができます。
必要に応じて、こういった情報も担当保育士に確認しておけば、安心して部分実習に臨めます。
部分実習時の導入をしっかり行う
主活動に入る前に、子どもたちに興味を持ってもらえるような導入をしっかり行いましょう。
例えば、制作であれば、実際に作った後どうやって遊べるかを端的に説明したり、材料に触ったりします。
これからやることにちなんだ手遊びや絵本も、良い導入になります。
普段から、担当保育士がどのような導入をしているか、時間配分も含めて観察して参考にしましょう。
部分実習後は丁寧な振り返りをして次回に活かす
部分実習後は、振り返りと反省の記録をすることが大切です。
子どもの様子や保育実習生の動き、対応などを振り返ります。
ねらい通りにできたか、予想していた子どもの姿と実際の動きや言葉との相違はあるか、どう対応できたかなどを分析し、反省点や気付きを記録します。
振り返りと記録をすることで次に活かすことができ、次の部分実習、責任実習がより良いものになっていくことでしょう。
また、担当保育士からも改善点やフィードバックをもらいましょう。
まとめ
部分実習は、今までの実習と違い、保育学生が主体となって保育する、いわばその時間を任される責任重大な時間です。
受け持ちのクラスの年齢や子どもたちの様子に合わせた遊びを設定し、準備をしっかり行い当日に臨みましょう。
・ねらいを明確にして、指導案をしっかり作成して準備をする
・担当保育士にマメに相談する
・普段から担当保育士や子どもたちの様子をよく観察しておく
これらを意識して部分実習に臨み、保育士スキルを身に付けていきましょう。

保育に関わる方たちとの交流を通じて、役に立つ情報を発信していきます。
関連記事一覧

最新記事