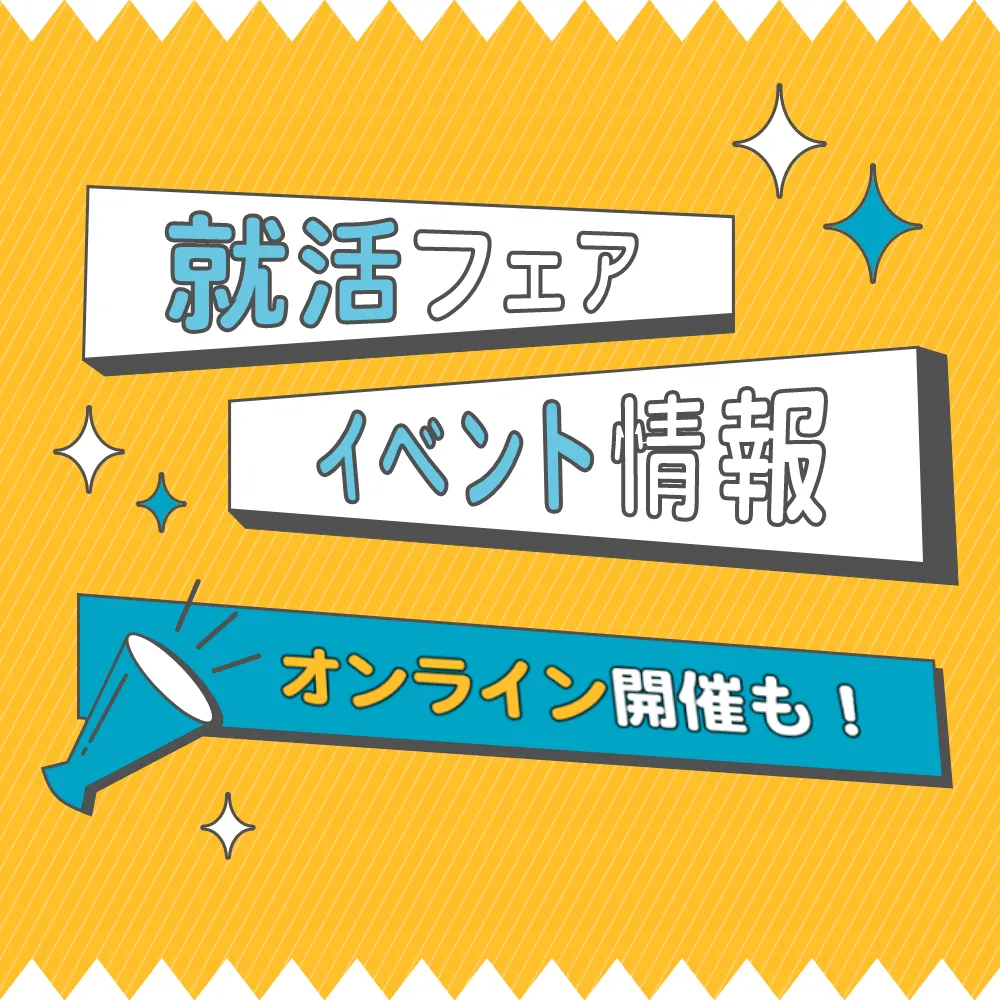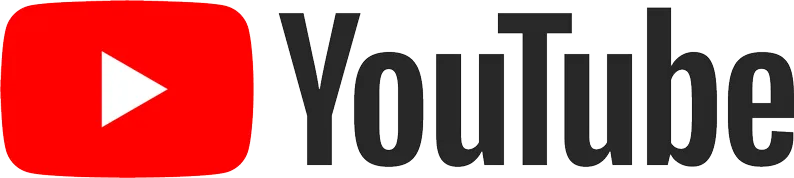【保育士試験】実技試験はどう対策する?試験内容と練習法を解説
保育士の実技試験は、「音楽」「造形」「言語」3つの出題科目から2科目選択し、受験します。
受験申請書を提出した後は変更が不可となりますので、よく考えて申請するようにしてくださいね。
事前にしっかりと準備して、当日を目指しましょう!
保育士試験の実技の科目や内容とは?

保育士の実技試験は「音楽」「造形」「言語」の3つの分野から、自分で選択した2分野を受験します。
それぞれの試験内容は、次の通りです。
■音楽表現に関する技術
音楽表現に関する実技試験は、保育士として求められる楽器演奏の技術や歌、リズム感に関する試験です。
試験ではピアノ、ギター、アコーディオンいずれかの楽器で伴奏をつけながら、課題曲とされる2曲を弾き語りします。
演奏しながら歌うというのはなかなか難しいので、しっかりと練習しておきましょう。
■造形表現に関する技術
造形表現では、保育の一場面を絵画で表現する試験が行われます。画材は、色鉛筆を使用します。
45分という制限時間内に情景や人物をイメージしながら豊かな色使いで描写し、表現することが求められるのですが、時間内に仕上げるというのがなかなか難しいので、事前にたくさん練習して、絵を描くことに慣れておきましょう。
他の実技試験とは違い、テーマは当日までわかりませんが、過去問題集や予想問題集などを使って、保育の場面を絵にする練習をしておくことをおススメします。
■言語表現に関する技術
言語表現の実技試験では、あらかじめ発表されている課題からひとつを選び、「3分間のお話」をします。
課題となるお話のあらすじを3分間にまとめ、子どもたちの集中力が継続できるように、身振りや手振りを交えながら話をしていきます。
子どもたちが楽しく話を聞けるように、言葉の繰り返しや擬音語を使って、盛り上がりを作りながらお話を進めていきましょう。
■実技試験の合格率は?
実技試験の合格率は、2005年から2015年の過去10年の統計によると82.5パーセントです。ちなみに、筆記試験の平均合格率は18.1パーセントです。
実技試験はきちんと対策をしておけば、比較的合格しやすい試験と考えられるでしょう。
実技試験の配点は、各科目50点の100点満点で、合格点が60点ですから、1科目につき30点ずつ取れればよい、ということになります。
絵や演奏が上手であること、話をするのがうまいことが合格の基準ではなく、保育士として子どもにどのように接しているかがポイントと考え、取り組んでください。
実技試験【音楽】の詳しい解説

実技試験の詳細は、以下の通りです。
■音楽の実技試験内容
音楽に関する実技試験では、子どもたちに歌いながら聞かせる想定で、2曲の課題曲を弾き語りします。
■試験官が見ているポイント
試験官は、演奏が上手かどうかをチェックしているわけではありません。子どもに音楽を聴かせるためのスキルがあるかどうかを確認しています。
実際に試験の場に子どもたちはいませんが、一緒に歌っている気持ちで、楽しく、元気に歌いましょう。
■試験の条件や課題曲
音楽に関する技術の過去の課題曲は、以下の通りです。
2022年
1.『小鳥のうた』(作詞:与田凖一 作曲:芥川也寸志)
2.『びわ』(作詞:まど・みちお 作曲:磯部俶)
2021年
1.『あひるの行列』(作詞:小林純一 作曲:中田喜直)
2.『揺籃(ゆりかご)のうた』(作詞:北原白秋 作曲:草川信)
2020年
中止
2019年
1.『どんぐりころころ』(作詞:青木存義 作曲:梁田貞)
2.『バスごっこ』(作詞:香山美子 作曲:湯山昭)
2018年
1.『おかあさん』(作詞:田中ナナ 作曲:中田喜直)
2.『アイ アイ』(作詞:相田裕美 作曲:宇野誠一郎)
・伴奏にピアノを選ぶ場合
ピアノを選ぶ場合は会場のピアノを使用し、課題曲2曲両方を演奏します。楽器の持ち込みは、必要はありません。
また、楽譜は市販のもの、または受験の手引きに掲載されている楽譜を使用します。
受験の手引きに掲載されている楽譜は簡易的なもので、コードのみ掲載されているため、自分で左手の伴奏を工夫する必要がありますので、その点は注意が必要です。
自分でアレンジして演奏するのが不安な場合は、市販されている楽譜のなかから自分が弾けそうなものを選んで、練習しておくと安心です。
1番のみを演奏しますが、前奏・後奏をつけたり、途中で移調してもかまいません。
・ギターで演奏する場合
ギターで演奏する場合は、楽器を持参する必要があり、アコースティックギターを用いることが条件となっています。
アンプの使用は不可で、カポタストは使用可能です。
ギターの場合は課題曲のうちから1曲を選び、演奏します。
楽譜は、受験の手引きに掲載されている楽譜を使用して演奏しますが、ギターの場合はアレンジする必要はなく、コードを尊重して演奏することが重要視されています。
1番のみを演奏し、前奏・後奏をつけるのは自由となっています。
途中で移調してもかまいません。
・アコーディオンで演奏する場合
アコーディオンで演奏する場合も、自分で楽器を持参する必要がありますから、楽器を持っている場合のみ選択するようにしてください。
独奏用のアコーディオンを用いることが、条件となっています。
アコーディオンの場合は課題曲のうちから1曲を選び、演奏します。
楽譜は、受験の手引きに掲載されている楽譜を使用し、基本的にアレンジは不要です。楽譜のコードを尊重して演奏することを大切にしてください。
1番のみを演奏し、前奏・後奏をつけるのは自由となっています。
途中で移調してもかまいません。
■音楽の実技試験 対策のポイントは?
音楽の実技試験のポイントは、楽器と声の大きさのバランスを考えて演奏することです。
歌声が子どもたちに届くように歌う必要がありますが、だからといってあまりにも大きな声で歌うと子どもたちも驚いてしまいます。
また、楽器の音が大きすぎて、歌声が聞こえないというのも困りますよね。
声と楽器のバランスを考えながら演奏し、どうしても声が出ない場合は選曲が自分に合っているかを見直してみましょう。
転調してもよいとされていますから、必要に応じてキーを変えてみてもいいかもしれません。ただし、転調はなかなか難しいので、曲自体を変更することも検討してみるといいでしょう。
参考:一般社団法人全国保育士養成協議会「令和4年実技試験概要」
実技試験【造形】の詳しい解説

造形は、保育園での活動の様子について、色鉛筆で描いて表現する試験となります。
音楽と言語の実技試験は、課題があらかじめ発表されていますが、造形だけは当日まで課題が公表されないのが特徴です。
■造形の実技試験内容
造形の実技試験は、保育の状況をイメージした造形表現ができるかどうかが問われる試験です。問題文と条件は、試験当日に発表されますので、その内容の一場面を、条件を守って表現します。
試験時間は45分間で、回答用紙のサイズはA4判となっており、用紙の種類は試験当日に提示されます。
ちなみに、2022年度の保育士前期試験では、フィンガー・ペインティングをしている3歳児の子どもたちと保育士の様子を描くというものがありました。
条件は「フィンガー・ペインティングで楽しく遊ぶ様子を描く」「園庭での準備の様子がわかること」「子ども3名、保育士1名以上を描く」「枠内全体を色鉛筆で着彩する」の4つでした。
■試験官が見ているポイント
造形の実技試験では、上手な絵が求められているわけでも、芸術作品を求められているわけでもありません。
試験官は、園児に伝わりやすい、ポイントを押さえた絵が描けているかをチェックしています。
難しく考えすぎずに対策をしていきましょう。
■試験の条件や課題内容
造形の実技試験では、持ち物が必要です。以下のものを用意しましょう。
〇鉛筆またはシャープペンシル
HBから2Bのものを用意します。
〇色鉛筆
12色から24色程度のもので、熱摩擦で消えるものや、クレヨン・クレパス・マーカーペンなどでは受験できません。
水溶性色鉛筆の使用は可能ですが、水分の塗布はNGです。
携帯用鉛筆削りを会場に持ち込むことは可能ですが、試験中に使用する際には試験監督員の了承が必要となりますので、注意しましょう。
〇消しゴム
〇腕時計
腕時計はアラーム音が鳴らないもので、計算機能や電話等の通信がついたものは不可となっています。
持ち物は、すべて人物のイラスト入りのものは不可となっています。
また、受験者同士での道具の貸し借りも認められていませんので、忘れ物のないように準備しましょう。
■造形の実技試験 対策のポイントは?
造形の実技試験では、絵を見た人がテーマを理解できるような、わかりやすい表現が必須となります。
また、見た人の気持ちが明るくなるような、健康的で明るい色彩で描くことも重要です。
人物の表情も、伝わりやすさを重視して描くようにしましょう。
絵全体の構図や、配置などのバランスも大切になりますから、まずは全体像をイメージしてから描き始めてくださいね。
参考:一般社団法人全国保育士養成協議会「令和4年実技試験概要」
実技試験【言語】の詳しい解説

言語の実技試験では、3歳児クラスの子どもたちに3分間のお話をすることを想定して行われます。
■言語の実技試験内容
課題のなかからひとつを選び、子どもたちが興味を持って、集中して聞けるような話ができるかを確認する試験です。
課題は、「ももたろう(日本の昔話)」、「3びきのこぶた(イギリスの昔話)」、「おおきなかぶ(ロシアの昔話)」、「3びきのやぎのがらがらどん(ノルウェーの昔話)」のなかからひとつを選び、一般的なあらすじを3分程度にまとめ、話をします。
■試験官が見ているポイント
言語の実技試験では、保育士として求められる基本的な声の出し方や、表現上の技術、幼児に対する話し方についてチェックされます。
■試験の条件や課題内容
子どもに見立てた椅子が前方にある状況で、話をします。
お話をする際には、立っていても、座っていてもいいので、自分が話しやすいスタイルで行いましょう。
開始の合図があったら、子どもたちに向けて題名を言うところから始めます。
絵本や道具の使用はNGで、3分間途中退出も不可です。
絵本などを手に持つことも想定する必要はありませんので、子どもたちのイメージがふくらむように身振り・手振りを加えながら話をしてください。
試験はタイマーで計って行います。
■言語の実技試験 対策のポイントは?
言語の実技試験では、子どもたちに伝わるお話ができるかが大事です。
3分間でお話をするには、文字数にすると600文字から800文字程度のシナリオが必要です。
シナリオにまとめるところから、練習を始めましょう。
シナリオが完成したら、スマートフォンやタブレットに録音して、ぜひ自分の声を聴いてみてください。
当日、台本などを見ることは禁止となっていますから、お話を何も見ずにできるようにする必要があります。
お話を記憶できたら、身振りや手振りを加えて、子どもたちに楽しんでもらえるように工夫し、最終的には家族や友だちに見てもらって感想を聞いてみてください。
コツとしては、登場人物が複数名の場合は声の高さで違いを出すことや、場面が変わるときは1拍置くことを意識しましょう。
参考:一般社団法人全国保育士養成協議会「令和4年実技試験概要」
実技試験を受験する際のポイント

実技試験を受験する際には、どのような点に注意すべきなのでしょうか。
■科目の選び方
科目の選び方に、決まりはありません。
自分が高得点を出せそうな、得意なものを選ぶようにしましょう。
受験申込時には科目を決めなくてはいけないので、試験内容をしっかりと確認し、選ぶようにしてください。
■過去の試験問題を必ずチェック
科目を選ぶ際には、過去にどのような問題が出題されていたかも見ておきましょう。
公式サイトにも、詳細が掲載されています。
一般社団法人全国保育士養成協議会「過去の試験問題」
■実技のみの再受験も可能
筆記試験は通過したものの、もし実技試験が不合格だった場合は、実技試験のみ再受験することも可能です。
ただし、筆記試験は3年間の有効期限があります。
3年以内に、実技試験に合格できるようにしっかりと準備しておきましょう。
実技試験は子どもたちと一緒に楽しむ気持ちで挑んで!
試験監督の前で実技をするのは、緊張しますね。
過去問題をよく分析し、解説などを読みながら自分なりのやりかたを見つけておくことが、合格への近道です。
本番は、目の前に子どもたちがいると思って、楽しく取り組んでくださいね!

保育に関わる方たちとの交流を通じて、役に立つ情報を発信していきます。
関連記事一覧

最新記事